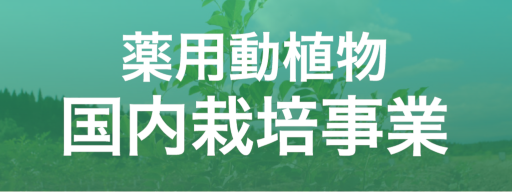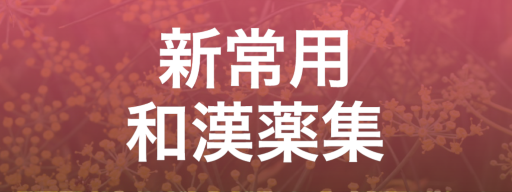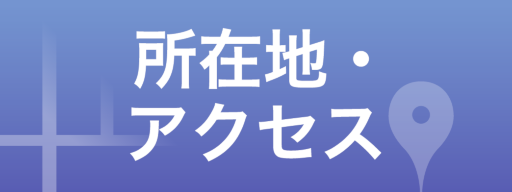新常用和漢薬集
| 名称 |
アカメガシワ
第十八改正日本薬局方 収載
|
||
| 英名 | Mallotus Bark | 生薬ラテン名 | MALLOTI CORTEX |

生薬名:アカメガシワ |

植物名:アカメガシワ |
||
| 基原 | アカメガシワ Mallotus japonicus Muëller Argoviensis (Euphorbiaceae トウダイグサ科)の樹皮 | ||
| 調製 | 樹皮のはがれやすい初夏に主として太い枝の皮を採取し,陰干しする. | ||
| 産地 | 日本(本州,四国,九州,沖縄),朝鮮半島,中国南部,台湾 | ||
| 性状 |
板状又は半管状の皮片で,厚さ1 ~ 3 mm,外面は帯緑灰色 ~ 帯褐灰色で,灰白色 ~ 褐色の皮目が群をなし,縦しま状の模様として認められる.内面は淡黄褐色 ~ 灰褐色で多数の縦線を認めるが,平滑である.折りやすく,折面はやや繊維性である. 僅かににおいがあり,味はやや苦く,僅かに収れん性である. |
||
| 成分 |
イソクマリン類:bergenin(日局18確認), 11-O-galloylbergenin, 4-O-galloylbergenin, 11-O-galloyldemethylbergenin フラボン類:rutin タンニン:mallotinic acid, mallotusinic acid, geraniin, corilagin, ellagicacid, 3, 3',4-tri-O-methylellagic acid, (-)-epigallocatechin gallate 強心配糖体:mallogenin-3-O-α-l-rhamnopyranoside, mallogenin-3-O -β-d-glucopyranosyl-(1→4)-α-l-rhamnopyranoside, panogenin-3-O-α-l-rhamnopyranoside, panogenin-3-O-β-d-glucopyranosyl-(1→4)-α-l-rhamnopyranoside, coroglaucigenin-3-O-l-rhamnopyranoside, coroglaucigenin-3-O -β-d-glucopyranosyl-(1→4)-α-l -rhamnopyranoside, corotoxigenin-3-O -α-l -rhamnopyranoside, corotoxigenin-3-O-β-d-glucopyranosyl-(1→4)-α-l-rhamnopyranoside, corotoxigenin-3-O-β-d-glucopyranosyl-(1→6)-β-d-glucopyranosyl-(1→4)-α-l-rhamnopyranosideなど |
||
| 選品 | 皮が薄く,脆くなく,丈夫なものが良い. | ||
| 適応 | 民間薬として胃潰瘍,十二指腸潰瘍,胃腸疾患,胆石症などに用いられる. | ||
|
漢方 処方例 |
漢方処方には用いられていない | ||
| 貯法 | 密閉容器 | ||
| 備考 |
日本薬局方には,日本名別名(漢字名)の規定はない.赤芽槲(あかめがしわ)は,日本薬局方外生薬規格2022の「アカメガシワエキス」では,日本名別名として「赤芽柏エキス」の漢字を用いている. 葉や種子は,赤色系草木染めの材料に用いられる.今日でも,アカメガシワを北陸,紀州,四国などでサイモリバ(菜盛葉)と呼び,また飯を盛る葉を意味するカシワ,あるいはお菜をのせるのに供するサイモリバの名称で呼ぶところが多い. アカメガシワの名称は,若葉が鮮紅色で花のように美しく,葉がカシワの葉に似ていることによる.サイモリバ,ミソモリバ(味噌盛葉)などの方言は,昔,食料品を盛ったりした名残と考える. |
||
情報更新日 2022/08/01 | |||